ベタの飼いかた

もっとも一般的なベタ・スプレンデンスの特徴、飼育方法について紹介します。
東南アジア原産のベタは「闘魚」とも呼ばれオス同士を一緒にすると、どちらか一方が死ぬまで闘うので、必ず一匹ずつ分けて飼うようにしてください。一匹ずつなら他の小型魚と一緒に飼うことができます。
ベタの特徴 その1 呼吸について
 ベタはもともとタイなどの沼や池、小さな水溜まりの様なところにも生息している種類です。ベタはエラ呼吸の他にラビリンス器官を持っているため空気から直接呼吸が可能な魚です。そのためエアーレーションのない環境でも生活が可能です。逆に流れが激しいと泳ぎが得意ではないベタは弱ってしまいます。このような理由から、ビンや小さいケースでも飼育が可能です。
ベタはもともとタイなどの沼や池、小さな水溜まりの様なところにも生息している種類です。ベタはエラ呼吸の他にラビリンス器官を持っているため空気から直接呼吸が可能な魚です。そのためエアーレーションのない環境でも生活が可能です。逆に流れが激しいと泳ぎが得意ではないベタは弱ってしまいます。このような理由から、ビンや小さいケースでも飼育が可能です。
ベタの特徴 その2 色、形について
ベタの魅力はなんといってもカラーバリエーションが多いことです。赤、青、緑、白、黒、黄色等や、最近ではメタリックな色もあります。
また、形は一般的な尾の長いトラディショナルや、ケバケバした尾のクラウンテール、背ビレが大きく尾が二つに割れたダブルテールやスーパーデルタ、ハーフムーンといった扇状の尾ビレを持つショーベタ、闘魚のために改良された尾の短いプラガット等様々な品種があります。
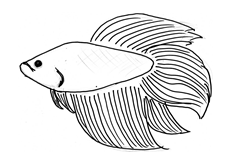
トラディショナル
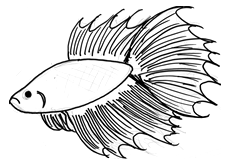
クラウンテール
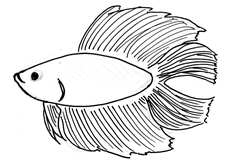
ダブルテール
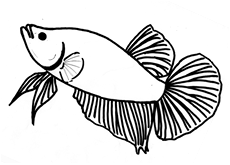
プラガット
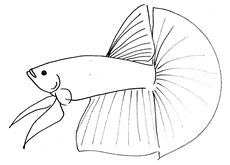
ショーベタ
ベタの特徴 その3 闘魚としての性質
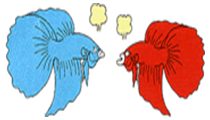 ベタはオス同士が激しく戦い合う魚として有名です。同じ水槽に複数のオスを入れると噛み付き合いのケンカになりどちらかが死ぬまで戦います。そのためオスは1匹づつ単独飼育することになります。
ベタはオス同士が激しく戦い合う魚として有名です。同じ水槽に複数のオスを入れると噛み付き合いのケンカになりどちらかが死ぬまで戦います。そのためオスは1匹づつ単独飼育することになります。
また、オスはメスに対しても威嚇するので、繁殖の時以外は別々に飼育います。メス同士であれば混泳も可能ですが小競り合いはしますので、水草など多めのシェルターが必要です。
オスは他種の魚に対しては穏やかな性格なので、ベタとあまり大きさの変わらないおとなしい魚とは混泳可能です。その場合はベタが痩せたり傷ついていないか注意してください。
ベタの飼育に必要なもの
ベタはビンでも飼える魚ですが水質維持、保温管理は水槽のほうがしやすいので、水槽飼育で最初に必要なものを説明します。
①水槽
ベタに対してできるだけ多くの水を用意すると水質も安定します。7リツトル程度あると良いです。
②ヒーター
ベタは熱帯魚です。一年を通して25~28℃が適温です。冬場はヒーターが必需品です。
低温になると弱り死んでしまいます。水槽に入れる熱帯魚用ヒーターかパネルヒーターがおすすめです。
③水質調整剤
水道水の塩素を抜くカルキ抜き、バクテリア液、弱酸性に傾けるPH調整剤など。
④エサ
ベタ用の人工餌が一般的です。1日1回~2回4~5粒程度与えます。たくさん与えると水を汚します。
⑤スポイト
水槽の下に沈んだゴミを取るのに使います。
⑥その他
砂利や水草、水温計、小網、流れの激しくない濾過器、水槽用ライト、マジックリーフ※など。
※マジックリーフ…水を弱酸性に傾ける落ち葉。水は茶色くなりますがベタに適した水を作れます。
ベタの日常管理
ベタの平均寿命は2~3年程度です。保温や水換えの管理をしっかりして長く健康に飼育しましょう。
①換水
ベタは水の汚れに弱いですが急な水質の変化にも弱い魚です。水換えは水の汚れ具合にもよりますが3日~1週間に一度、換える量は1/5から多くても半分程度にして古い水を残します。その時スポイトでできるだけ汚れを取り除きましょう。ベタは弱酸性(pH6.5~7)の水質を好みますので適した水質を作りましょう。
②フレアリング
オスのベタは長い尾ヒレが特徴ですが、広げる機会がないと固まって開かなくなってしまいます。そのため時々、鏡や他のオスを見せてヒレを広げさせることでヒレの健康を保ちます。これを「フレアリング」と呼びます。フレアリングによってヒレはより大きく、美しく育ちます。
③病気
水質の悪化や急変、水温の低下などが原因でベタが病気になることがあります。代表的な病気は体に白い点がつく白点病やコショウ病、ヒレが溶ける尾腐れ病などです。初期であれば原因の改善と同時に魚用の薬や塩水浴(水に対して1%程度の天然塩を入れる)、水温を30℃程度まで上げるなどの対処で治ります。
日常の管理がしっかりできていれば病気になりにくくなりますので、日頃から予防のための飼育をしましょう。
④旅行時
ベタは餌切れに強いので健康な状態なら1週間程度は餌を食べなくても大丈夫です。旅行などの際、無理に餌をたくさん与えていくと逆に水質が悪化して弱ってしまいます。できるだけ水量の多い水槽に入れ温度変化の少ないところに置きましょう。もちろん、預かってくれる人がいればより安心です。
ベタの繁殖
ベタ・スプレンデンスの繁殖から子どもの育て方について
ベタの繁殖の特徴
ベタはメダカや金魚とは少し違った方法で繁殖を行います。オスが水面に泡巣を作りメスの産んだ卵をオスがそこで守りながら育てます。
情熱的なその繁殖方法は他の魚にない魅力があります。また、色彩や尾の形のバラエティーが多いため自分好み色同士を掛け合わせたりする楽しみも魅力です。ベタは1回の繁殖で100~200程度の卵を産み上手く育てばかなりの数が殖えることとなります。
ベタは複数飼育が困難なため成長後も飼育できる環境を整えてから繁殖にチャレンジしましょう。
ステップ1 必要なものを集める
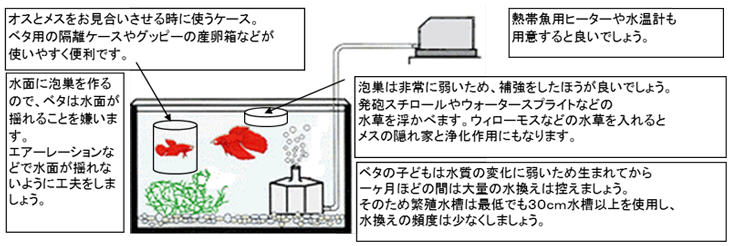
ステップ2 親を選ぶ
まず最初に大切なのは繁殖させたいベタが繁殖できる状態かどうかを確認することです。目安はオスの場合、水面にふっくらした大きな泡巣を作っている事。
メスの場合は卵を持っていると腹部が大きくなります。ショップで売られている時にはまだ成長しきってなかったり、卵を持っていないことも多いので飼い込んでから繁殖に挑むことが重要になります。前もって栄養価の高い餌を与えることで卵の数や大きさも良くなり生まれた子も上手く育ちやすくなります。また、ペアの相性が合わなかったりどうしても上手くいかない時の為に複数のベタを用意しておくと良い。
ステップ3 お見合い~産卵
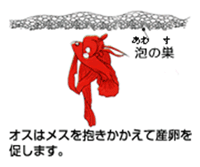 親の準備が整ったら先にオスを繁殖水槽に移します。オスがしっかりした泡巣を作った頃にメスを隔離ケースへと入れましょう。この状態で2~3日ほど様子を見ます。お互い近づこうとするようであればメスを水槽へ移します。
親の準備が整ったら先にオスを繁殖水槽に移します。オスがしっかりした泡巣を作った頃にメスを隔離ケースへと入れましょう。この状態で2~3日ほど様子を見ます。お互い近づこうとするようであればメスを水槽へ移します。
オスはアピールをしながらメスを泡巣へと誘導します。この時メスがついて行けば産卵が始まりますが、うまくついていかずオスが激しく追いまわしメスを攻撃するようであればメスを隔離ケースへ戻し再び様子を見ます。
産卵は何回にも分けて行われます。全て卵を産み終わるとオスだけが卵を守り始めるためここでメスは他の水槽へ移しましょう。これからはオスが落ちた卵や稚魚を拾い泡巣に運び世話をします。
ステップ4 孵化後
卵が産まれてから3~4日でふ化し、さらに3日ほどで泡巣にぶら下がっていた稚魚は自分で泳ぎ出します。いままで稚魚を守っていたオスはここで隔離します。最初の2~5日は口が小さくインフゾリア、バクテリアなどを食べて育ちます。バクテリアは水槽内に自然に発生するものですが少なく感じる時は市販のバクテリア液やたね水などを少量入れましょう。
その後ブラインシュリンプを食べるようになるので計画的に毎日増やして一日数回与えましょう。約1ヶ月の間はブラインシュリンプを中心に、食べるようであれば人工飼料も与えていくと良いでしょう。
孵化から1ヶ月以降はブラインシュリンプでは足りなくなりますので、糸ミミズや赤虫、人工飼料で育てましょう。徐々に生餌を減らし、人工飼料に慣らすようにします。(日数は目安です。成長スピードによって餌を調整して下さい。)餌をこまめに与えられるのであれば水温を高めに保つことで代謝が高まり、成長が早くなります。
換水は1ヶ月程の間は水質を極力変えないようにごく少量に抑えた方が良いでしょう。生後1ヶ月半頃から子どもの成長に差が出始めますが、そのまま放っておくと差が広がり成長の遅いベタが育たなくなってしまうため、水槽を分けて育てる必要があります。
ベタは兄弟であれば激しく争う事は少ないですが、一度水槽を分けると闘争心が強くなるため再び同じ水槽に入れる事はできなくなります。
ブラインシュリンプの増やし方
①1リットル程度の容器(ペットボトルなど)に水を入れ食塩20gを入れる。
②使う分のブラインシュリンプの卵を容器に入れる。
③25~28度の水温にし、エアーポンプでエアレーションをする。
④卵を入れてから22~24時間ほどで卵からふ化します。
⑤スポイトで産まれたブラインシュリンプを吸い取り、網などで食塩水を捨ててからベタに与えます。
※ブラインはふ化後数時間で脱皮をして一回り大きくなると同時にもって産まれた栄養を使ってしまうため栄養価が落ちてしまいます。ふ化させたらできるだけ早いうちにベタに与えましょう。
ステップ5 雌雄判別
体が3センチほどの大きさになってくると雌雄の判別が出来るようになります。判別のポイントは以下の通りです。
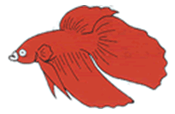
オス
- エラが大きくなる
- 各ヒレが大きく開く
- 尻ビレが長くなる
- 発色が良い
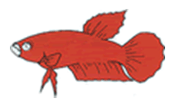
メス
- オスよりも体が小さい
- 体色も地味
- ヒレが大きくならない
- 肛門部に偽卵(白い点)がある
※基本的に全品種共通ですが発育の悪いベタやプラカットではやや識別が難しい場合があります。

